第二章 大衆の自然発生性と社会民主主義者の意識性
レーニンの問題意識の多くは「大衆の自然発生性」と「社会民主主義者(共産主義者)の意識性」をどのようにして結合するのかという点にあった。
レーニンは当時のロシアにおける運動の強みが大衆の(主として工業プロレタリアートの)覚醒にあり、弱みが革命的指導者の意識性と創意性の不足にあることを冒頭で明らかにし、この章のテーマを「革命的指導者の意識性と相違性」ということに絞って問題を提起しているのである。
→ 『ラボーチェエ・デーロ』は「自然発生的要素と意識的・『計画的』要素の相対的意義についての評価の相違」あるいは「自然発生的要素の意義の軽視」と批判しているが、レーニンによれば「自然発生的要素」とは、本質上、意識性の萌芽形態であり、労働者階級が自らを圧迫している資本・雇い人に抵抗して自然発生的に結合する能力、すなわち組織的能力を意味しており、それと社会民主主義者の「意識性」つまり革命理論が結びつく以外にはブルジョア社会の転覆はできないのである。どちらを重視するかとか、どちらが上に立つかというような問題のたて方そのものがナンセンスなのだ。
諸党派、諸潮流の党派性が労働運動と党との関係における「理論上・政治上の意見の相違の全核心」(P48)として表れている事をみれば、この問題の重要性は明らかである。
「だからこそ、意識性と自然発生性との関係という問題はきわめて大きな一般的関心をひ
くのであって、この問題について非常にくわしく論じなければならない」と強調している。
1)自然発生的高揚の始まり
1890年代、労働者のストライキがロシア全土に広がった。1860年代~70年代のストライキに比して90年代のストライキ運動は、明確な要求を提出したり、時期を考慮したりとはるかに多くの意識性のひらめきを示していた。
「…一揆が抑圧された人々の単なる蜂起でしかなかったのにたいして、組織的なストライキはすでに階級闘争の芽生えをあらわしていた。だが、あくまでも芽生えにすぎない。それ自体としてみれば、これらのストライキは、組合主義的闘争であって、まだ社会民主主義的闘争ではなかった。それらは、労働者と雇主との敵対のめざめを表示すものではあったが、しかし労働者は、自分たちの利害が今日の政治的・社会的体制全体と和解し得ないように対立しているという意識、すなわち社会民主主義的意識を持っていなかったし、また持っているはずもなかった。こういう意味で、90年代のストライキは『一揆』に比べれば非常な進歩であったにもかかわらず、やはり純然たる自然発生的な運動の範囲をでなかった」(P45)
→ 労働者階級以外の他の階級も自然発生的に決起し、闘争同盟のような組織を作ることは歴史的経験から明らかであるが、みずから恒常的に組織をつくるのはブルジョアジーへの隷属を余儀なくされている労働者階級が共同労働の経験をとおしてつくりあげる独特の能力である。そして、この能力はブルジョアジーとの闘いとして形成され発達し、みずからの権利と労働条件を守るために団結することで、ますますその力を高めていくのである。
ところで、社会民主主義的(共産主義的)意識というのは、労働者階級的利害が「今日の政治・社会体制全体と和解しえないように対立していると言う意識」であり、「この意識は外部からしかもたらしえないものだった。
労働者階級が、まったく自分の力だけでは組合主義的意識、すなわち、組合に団結し、雇主と闘争をおこない、政府から労働者に必要なあれこれの法律の発布をかちとるなどのことが必要だという確信しかつくりあげられないことは、すべての国の歴史の立証するところである」(P49)
→ 労働者は個別資本あるいは資本家の団体、またはその政府に対して労働条件の改善や権利の向上、さらには労働者保護のための制度の確立等々を要求し、産業別統一闘争やゼネストなどを打ち抜くことによって資本の譲歩をかちとることはできるかもしれない。しかし、どのような戦闘的な労働組合、激しい闘いも資本に雇われ続ける社会関係、生産体制を前提にするものであり、事実としても雇用と雇用の継続を要求するのであって、賃労働と資本の関係を解消するために闘うわけではない。
<資本を打ち倒し賃労働を廃絶し、資本家の政府に代わって労働者階級みずからを支配階級へと組織するという>革命闘争への意識は労働組合の経済闘争からは独自の理論をもって形成される以外ないのである。被支配階級としての労働者階級が、みずからを支配階級へと成長・飛躍させ、ブルジョア支配を打ち倒していくという意識、つまり「社会民主主義的(共産主義的)意識は外部から持ち込むほかはなかった」(P50)
「社会主義の学説は、有産階級の教養ある代表者であるインテリゲンチャによって仕上げられ、哲学・歴史学・経済学上の諸理論のうちから成長してきたものである。近代の科学的社会主義の創始者であるマルクスとエンゲルス自身も、その社会的地位からすればブルジョアインテリゲンチャに属していた」(P50)
ここでレーニンは、1890年代中ごろのロシアにおいてはどうであったかを検討している。
このころのロシアの社会民主主義者たちは経済的扇動に従事しながらも、そういう経済的扇動を自分たちの唯一の任務と考えなかったばかりか、反対に最初から一般にロシア社会民主党の最も広範な歴史的諸任務、とりわけ専制の打倒を提起することが重要と考えていた。
このように「1895~98年に活動していた社会民主主義者の一部(おそらくはその大多数さえも)が、「自然発生的」運動がはじまったばかりのその当時でも、もっとも広範な綱領と戦闘的戦術とを提出することが可能であると、まったく正当にも考えていたということを確認することが極めて重要である。
ロシアにおいても、「社会民主主義の理論的学説は労働運動の自然発生的成長とはまったく独立に生まれてきた。それは革命的社会主義的インテリゲンチャのあいだでの思想の発展の自然の、不可避的な結果として生まれてきたのである」。そして、90年代のなかごろにはそれが「労働解放」団の…綱領になって…、ロシアの革命的青年の大多数を味方にしていた。まさに、当時の社会民主主義者たちは、(「経済主義者」がいうように「条件がなかった」どころか)ストライキ闘争を専制にたいする革命運動にむすびつけ、抑圧のもとにさらされている人々を社会民主党のもとに獲得するために新聞の発行も試みられていた。
しかし、残念ながらこうした企画は権力の弾圧によって実現できなかった。それは当時の社会民主主義者に革命的経験と訓練が不足してからであり、(革命の事業では)この経験から学び、実践的教訓を引き出すためには、あれこれの欠陥や意義を完全に理解する(意識する)ことが必要である。
「経済主義者」たちは、欠陥を美徳にまつりあげ(→ 革命党の訓練不足という欠陥を直視せず、専制の打倒という任務方針が誤りであり、経済的扇動に重心を置くべきだという)
自分たちの自然発生性への屈従と拝跪を理論的に基礎づけようとさえしている。
2)自然発生性への拝跪 『ラボーチャヤ・ムィスリ』(注)
1897年の初めに「労働者階級解放闘争同盟」の「老人組」と「青年組」が「労働基金組合規約」をめぐって鋭く意見を対立させ、激しい論戦が行われた。これがのちのロシア社会民主党の二つの潮流の対立へと発展していく。
ここでレーニンが取り上げた『ラボーチャヤ・ムィスリ』の社説は「労働運動がこのような根強さを得たのは、労働者が自分の運命を指導者たちの手からもぎとって、ついに自分の手にそれをとりあげつつあるたまもの」だとか「政治はつねに従順に経済のあとに従う」と主張している。
事実は社会民主主義者、「闘争同盟」の組織者が憲兵の弾圧によって「労働者の手からもぎとられた」のであり、「経済主義」の主張は「前進するよう、革命的組織を固めるよう、政治活動を拡大するようによびかけようとはしないで、後退するよう、組合主義的闘争だけをやるよう」よびかけるものだったが、これが当時の青年大衆に大きな影響をおよぼしていた。
(注)『ラボーチャヤ・ムィスリ』=1897年から1902年に出された「経済主義者」の機関誌。 レーニンは国際日和見主義のロシアにおける変種と批判していた。
レーニンはこうした状況に対しで社会民主党内に浸透しつつある経済主義(『ラボーチェエ・デーロ』)を検討・批判する視点として3つの事情についてふれ、次の節で詳しく展開している。
第1の事情として、「意識性が自然発生性によって圧服されたのは、これまた自然発生的(外在的要因による力関係の変化の中でという意味?)におこなわれた」ことをあげ、「この圧服は二つの対立した見解が公然と闘って一方が勝った結果ではなく『老人組』の革命家が憲兵によって『もぎ取られ』、『青年組』がますます数多く舞台に登場してくることによっておこなわれた」ことを明らかにしている。(P59)
第2の事情として、すでに「経済主義」の最初の文筆上の極めて特徴的な現象として、彼ら(注)が自分たちの立場を擁護するのに、ブルジョア的な「純組合主義者」の論拠にたよらざるをえないということがある。
およそ労働運動の自然発生性のまえに拝跪すること、およそ「意識的要素」の役割、社会民主党の役割を軽視することは、とりもなおさず―その軽視する人がそれを望むと望まないとにはまったくかかわりなく―労働者にたいするブルジョア・イデオロギーの影響を強めることを意味する。(P50)
(注)一言でいえば「経済主義」だがレーニンは、①「純労働運動」の味方たち、②プロレタリア闘争との最も「有機的」な結びつきの礼賛者たち、③非労働者的インテリゲンチャの敵対者たちをあげている。
第3の事情として「経済主義」という名称が新潮流の本質を十分正確に伝えるものでないことがある。『ラボーチャヤ・ムィスリ』は政治闘争を全く否定しているわけではなく、政治はつねに従順に経済のあとに従うと考えているだけである。政治闘争の否定というよりも、むしろこの闘争の自然発生性の前に、あるいは無意識性にたいして拝跪するのである。
「組合主義は、往々考えられているように、あらゆる『政治』を排除するものではけっしてない。労組合は、つねにある種の(だが社会民主主義的ではない)政治的扇動や闘争をやってきた。」
『ラボーチャヤ・ムィスリ』は労働運動そのもののなかから自然発生的にするが、社会主義の一般的任務と当時のロシアの諸条件とに応じた(今日で言えば、それぞれの国内的条件に応じた)特有の意味での社会民主主義的政治を自主的=意識的に作り上げることをまったくやらなかったのである。
→ レーニンは前節において「社会民主主義的意識は外部からもちこむほかはなかった」と述べているが、前述の3つの事情のうちの第2の事情の中で、特にこの問題をカウツキーのオーストラリア社会民主党の新綱領草案批判を引用して展開している。(言葉の当否には議論のあるところだが)これがいわゆる「外部注入論」である。
引用されているカウツキーの論述の主要な点を4点にまとめると次のようになる。
①学説としての社会主義はプロレタリアートの階級闘争と同じく、今日の経済関係のうちに根ざしており、またそれと同じく、資本主義の生み出す大衆の貧困と悲惨にたいする闘争のうちから成立してくる。(注)
②社会主義と階級闘争は、並行して生まれるものであって、一方が他方から生まれるものではなく、またそれぞれ違った前提条件のもとで生まれるのである。今日の経済科学はたとえば今日の技術と同じく、その担い手はプロレタリアートではなく、ブルジョア・インテリゲンチャである。近代社会主義もやはりこの層の個々の成員の頭脳の中から生まれた。
③まず、はじめに知能のすぐれたプロレタリアに伝えられたのであって、ついでこれらのプロレタリアが事情の許すかぎりでプロレタリアートの階級闘争のなかにそれをもちこむのである。
④だから、社会主義的意識はプロレタリアートの階級闘争のなかへ外部からもちこまれたあるものであって、この階級闘争のなかから自然発生的に生まれてきたものではない。したがって、プロレタリアートのなかに自分たちの地位と自分たちの任務とについての意識を持ち込む(=自覚を促す)ことが社会民主党の任務である。
この引用の結論として、レーニンは次のようにまとめている。
労働者大衆自身が彼らの運動の過程それ自体のあいだに独自のイデオロギーをつくりだすことが考えられない以上(注)問題はこうでしかありえない。
①ブルジョア・イデオロギーか、社会主義イデオロギーか、と。そこには中間はない。(な
ぜなら、人類はどんな「第三の」イデオロギーもつくりださなかったし、…階級外の、あるいは超階級的なイデオロギーなど決してありえないからである)
②だから、およそ社会主義的イデオロギーを軽視すること、およそそれから遠ざかることはブルジョア・イデオロギーを強化することを意味する。
③労働運動の自然発生的な発展は、まさに運動をブルジョア・イデオロギーに従属(屈服)させる方向にすすむ。なぜなら、自然発生的な労働運動とは組合主義であり、〔純組合主義〕であるが、組合主義とは、まさしくブルジョアジーによる労働者の思想的奴隷化を意味するからである。だから、われわれの任務、すなわち社会民主党の任務とは、自然発生性と闘争すること、ブルジョアジーの庇護のもとに入ろうとする組合主義のこの自然発生
性的な志向から労働運動をそらして、革命的社会民主党の庇護のもとにひきいれることである。(P63)
(注)ところで、労働者階級が社会主義的イデオロギーをつくりあげる仕事にまったく参加しないだろうか、そうではない。ただし、その場合にはプロレタリアとしてではなく、社会主義の理論家として社会科学の学習、理論的研究に参加する。そして彼らは労働者の中でその意識水準を高め、社会主義の思想を広めると同時に、自ら獲得した理論を実践的に検証するために極力骨をおるのである。
また、レーニンは「自然発生的運動、最少抵抗線を進む運動がなぜブルジョア・イデオロギーの支配に向かってすすむのか?」として、それはブルジョア・イデオロギーが社会主義イデオロギーより、その起源においてずっと古く、いっそう全面的に仕上げられていて、はかりしれないほど多くの普及手段(→ 特に今日の帝国主義国におけるその社会的=政治的経済的物質力はロシア革命当時とは比べものにならないほどである)をもっているためである」として、だからこそこれとの闘いが重要であることを訴えている。
(社会主義者が反動的な労働組合や組織の中でも、そこに労働者が存在する限りはうまずたゆまず活動しなければならないという原理は、そうしなければ労働者階級はいっそう深くブルジョア・イデオロギーのもとに隷属させられるということ、またこのことに無頓着であるということは、みずからの陣地を敵に明け渡すにひとしく、およそ革命を語ることそのものが空論でしかない)
【いわゆる「外部注入論」の考え方】
往々にしてレーニンが労働者の自然発生性はダメなんだ、と言っているかのように誤解され、さらには「無知な労働者に知識のあるインテリ活動家が理論を吹き込む」と言った反共イデオロギーの宣伝にさえ使われている。しかし、これはレーニン組織論の核心をなす部分であり、正確に理解することが是非とも必要である。
① レーニンは『一歩前進、二歩後退』の中でも、「資本主義によって訓練されたプロレタリアート」と規定し、また『論集十二年間』の序文においても「客観的な経済的理由から最大の組織能力をもつプロレタリアート」と述べているように、労働者階級の自然発生的能力を客観的、歴史的なものとして積極的に評価しているのである。これはマルクスの『共産党宣言』でも明らかにされている核心的内容でもある。
革命は、労働者階級のこの組織能力(労働者階級が自然発生的に結合し、団結していく革命的能力)と結びつくことなしには成し遂げることができない。
しかし、プロレタリアートは資本と賃労働が本質的、非和解的に対立しているという感覚は自らの歴史的経験をとおして獲得できる(※注)が、自分自身の歴史的、経済的存立基盤である資本主義の体制そのものを転覆し、プロレタリアートの権力と置き換えなければならないという共産主義的意識(イデオロギー)は自然発生的な闘争のなかからは身につけることはできない。レーニンが強調しているのは、この関係をはっきりさせることなのである。
※注)「ある人には脅し道具としか見えない工場こそ、まさにプロレタリアートを結合し
訓練し、彼らに組織を教え、彼らをその他すべての勤労・被搾取人民層の先頭に立たせた
資本主義的協業の最高形態である。資本主義によって訓練されたプロレタリアートのイデ
オロギーとしてのマルクス主義こそ、浮動的なインテリゲンチャに、工場が備えている搾
取者の側面(餓死の恐怖に基づく規律)と、その組織者としての側面(技術的にも高度に
発達した生産の諸条件によって結合された共同労働に基づく規律)との相違を教えたし、
いまも教えている。ブルジョア・インテリゲンチャには服しにくい規律と組織をプロレタ
リアートは、ほかならぬ工場というこの『学校』のおかげで、特にやすやすとわがものに
する」(『一歩前進、二歩後退』)
②「労働者階級は自然発生的に社会主義に引きつけられる」(労働運動の階級的、自然成長的発展の延長上に革命を描こうとする「経済主義者」の論拠でもある)という見方について。
この言葉が正しいのは、「社会主義理論は、最も深く、また最も正しく労働者階級の困苦の原因を示しているので、…労働者はこの理論をきわめて容易にわがものにする、という意味である」(P67)
ただし、現実の過程は「労働者階級は自然発生的に社会主義にひきつけられるが、それにもかかわらず」、(労働者が自然発生の前に降伏し、意識性をもたなければブルジョア社会の中で)「最も多く押し付けられてくるものは、最も普及しているブルジョア・イデオロギーである」
③学説としての社会主義理論はブルジョア・インテリゲンチャによって成立したものであるが、その出発点は資本主義が生み出す経済関係、その貧困と悲惨に対する労働者階級の闘い、この怒りに根拠をおいているということである。この点を否定ないし曖昧にしてプロレタリアートを解放の主体として位置づけない場合には、労働運動はたんなる救済運動、空想的社会主義でしかなくなる。
④「外部から持ち込む」という意味についてレーニンは次章の第5節で「階級的・政治的意識は、外部からしか、つまり経済闘争の外部から、労働者と雇い主との関係の圏外からしか、労働者にもたらすことができない」と誤解の生じようのない言い方で明確に述べている。
資本主義の国家そのものを打倒するという立場にたつためには、革命のための理論が必要であり、それは労働者の運動の中から自然発生的には作られない、経済闘争の外部からしかもたらし得ない。そして、もうひとつ労働者階級の政治意識の成長を阻んでいるのは彼らの全生活を覆うブルジョア・イデオロギーの洪水なのである。
したがって、「持ち込む」の意味は、労働者をブルジョア・イデオロギーの影響から遠ざけ、「自然発生的な経済闘争」に対して「意識的な政治闘争」に目を向けさせること。
そのためには労働者階級の闘いの中だけではなく、あらゆる階級、階層の政治的現れに精通し、それを暴露できる特定の組織をつくることが必要だ、ということを提起しているのである。
⑤「社会主義理論がプロレタリアートの階級闘争と別個に成立した」ということを強調するあまり、学説としての社会主義理論を階級闘争から切り離し、労働者階級の闘いとは無縁な純粋理論として成立したかのように描き出すこと、これを階級闘争の場に持ち込むことが必要なのだ、と理解する誤りである。スターリン主義は、労働運動の自然発生的要素を蔑視し、労働者の主体性を無視し、党の路線を労働組合に「外部から持ち込み」押し付け る、いわゆる「引き回し」を行ってきたのである。
3)「自己解放団」と『ラボーチェエ・デーロ』
・『ラボーチャヤ・ムィスリ』(「労働者の思想」)
創刊号1897年10月
・『労働者自己解放団の檄』 1899年3月
・『ラボーチェエ・デーロ』創刊号 1899年4月
『ラボーチャヤ・ムィスリ』は初めから経済主義潮流としての姿をだれよりもあざやかに示していたが、少し遅れて『労働者自己解放団の檄』も同様の結論をひきだし、経済主義の特徴を鮮明にした。ついで活動を開始した『ラボーチェエ・デーロ』は、はじめから「経済主義者」を「擁護した」だけでなく、自らもたえず「経済主義」の基本的誤謬に迷い込んでいった。この誤りの根源は、彼らの綱領のなかにある「大衆運動が『任務を規定する』」という命題に対する理解、これへの態度をめぐる対立に問題の核心があった。
「これは二とおりの意味に理解することができる。すなわち、この運動の自然発生性の前に拝跪するという意味、つまり、社会民主党の役割を、あるがままの労働運動への単なる奉仕に帰着させるという意味(これが、『ラボーチャヤ・ムィスリ』、『自己解放団」その他の『経済主義者』の理解である)」そして、もう一つは「この大衆運動が発生する以前の時期にはそれで足りていた任務にくらべて、はるかに複雑な、あたらしい理論上、政治上、組織上の諸任務を大衆運動がわれわれに提起するという意味」にも理解することができた。
そして、この第一の理解に傾いていた『ラボーチェエ・デーロ』は、「大衆的労働運動にたいして専制の打倒を第一の任務として提起することはできないと考えて、この任務を(大衆運動の名において)最も身近な政治的要求のための闘争という任務に低めた」(P72~73)
→『ラボーチェエ・デーロ』第7号(ペ・クリチェフスキーの論文)の引用
「政治闘争における『段階論』」(P74)
「政治的要求は、その性格上、全ロシアに共通であるが、しかし、はじめは」「当該の労働者層(原文のまま!)が経済闘争から引きだした経験に合致するものでなければならない。この経験にもとづいてのみ(!)、政治的扇動に着手することができるし、また着手しなければならない」「マルクスとエンゲルスの学説によれば、個々の階級の経済的利益が歴史上決定的な役割を演じるのであり、したがって、とくに自己の経済的利益のためのプロレタリアートの闘争が、プロレタリアートの階級的発展と解放闘争とによって、第一義的な意義をもたなければならない…」
これに対して、レーニンは次のように批判している。
「経済的利益が決定的な役割を演ずるからといって、したがって経済闘争(労働組合闘争)が第一義的な意義を持つという結論には、けっしてならない。なぜなら、諸階級のもっとも本質的で、『決定的な』利益は、一般に根本的な政治的改革によってはじめて満足させることができるし、とくにプロレタリアートの基本的な経済的利益は、ブルジョアジーの独裁をプロレタリアートの独裁でおき代える政治革命によって、はじめて満足させることができるからである」(74P)
→『ラボーチェ・デーロ』第10号の主張
「行いうる闘争こそのぞましく、そして現瞬間に行われている闘争こそ、行いうる闘争である」「計画としての戦術はマルクス主義の基本精神とあいいれない」「戦術とは『党とともに成長する党任務の過程』」
レーニンは、こうした主張こそが、自然発生性に拝跪する、日和見主義潮流の綱領そのものであると指弾し、「マルクス主義にたいする中傷であり、かつてナロードニキがわれわれとのたたかいにあたってえがいてみせた、まさにあの戯画に、マルクス主義を変えてしまうものである」と批判する。
そして、「国際社会民主主義者の全歴史は、あるときは甲の、あるときは乙の政治的指導者によって提出された計画で満たされており、ある人々の政治上・組織上の見解の先見と正しさを実証し、他の人々の短見と政治的誤謬をあからさまにしている」(P76)
「歴史がその最後の判定をくだしてから多くの年月がたったあとで、昔をかえりみ、党とともに成長する党任務の成長という格言によって自分の深遠さを示すのは、もちろんむずかしいことではない。しかし、ロシアの『批判家』や『経済主義者』が社会民主主義を組合主義に低めており、またテロリストが、古い誤りを繰り返す…混乱の時期にこのような深遠な迷論でことをすませるのは、自分自身に『貧困証明書』を発行するというもの」「多くの社会民主主義者が、ほかならぬ創意と精力に不足し、『政治的宣伝、扇動、組織の規模』に不足し、革命的活動をいっそう広範に組織するための『計画』に不足している時期に『計画としての戦術ということはマルクス主義の基本精神にあいいれない』などとかたるのは、理論的にマルクス主義を卑俗化するだけでなく、さらに実践的に党をうしろへ引きもどす」(P77)ものだと断罪している。
また、「マルクス主義が意識的な革命的活動に正しくも巨大な意義を与えていることに心を奪われて、実践上では。発展の客観的あるいは自然発生的要素の意義の軽視におちいっている」という『イスクラ』への批判にこたえて次のように反論している。
「もし主観的計画の立案者(=経済主義者)が客観的発展を『軽視する』とすれば、それはどういう点に現れるだろうか?この客観的発展があれこれの階級や階層や集団、あれこれの民族や民族群などを、あるいはつくりだし、あるいは強め、あるいは滅ぼし、あるいは弱めそれによってあれやこれやの国際的な政治的勢力編成や、革命的政党の立場等々を条件づけていることを…見おとす点に現れる」(つまり意義の軽視とか重視とかいう問題ではなく)指導者は具体的な「客観的発展を正しく理解する意識性」が必要なのだと言っている。
最後に結論として、ロシア社会民主党内の「新しい潮流」の基本的誤りは、自然発生性の前に拝跪する点に、すなわち「大衆が自然発生的であればこそ、われわれ社会民主主義は多くの意識性をもつ必要があることを理解しない点にあることを確信するにいたった」「大衆の自然発生的な高揚が大きければ大きいほど、運動がひろまればひろまるほど、社会民主主義派の理論活動においても、政治活動においても、組織活動においても、多くの意識性をもつ必要が、くらべものにならないほどいっそう急速に増大する」(82P)
そして、1890年代のロシアの革命運動は「理論」でも活動でも大衆運動の自然発生的高揚に立ち遅れてしまい、運動全体を指導する能力のある、中断のない、継承性のある組織をつくりだすことができなかった。この巨大な任務を成し遂げるためには、①対政治警察との闘いにおいて、②理論、政治、組織活動において訓練を欠いていた。と総括している。
また、革命党の指導者の意識性、役割とは「いろいろな問題にあらかじめ理論的に解答をあたえ、そのあとで(実際の経験を通して)この解答の正しいことを組織にも、党にも大衆にも納得させる」ということであり、そうして「大衆運動を『自分の綱領』のところまで引き上げる」ことこそが社会民主主義党の役割なのだ、と言っているのである。
経済主義に迷いこむ根源的理由は、大衆追随主義にあるということ。裏返せば意識的活動の困難さ、壁の厚さの前に圧倒され、自然発生性の前に拝跪し、その範囲での闘いこそが党の一義的任務であると信じ込むのである。大衆運動の発展が、共産主義者、革命党に突きつけている革命的役割、任務をあらかじめ推理し研究し、それに応えぬくことこそが革命党たらしめる、ということ。それ以外のことで大衆運動が問題を解決する、ということはない。
(第3回に続く)

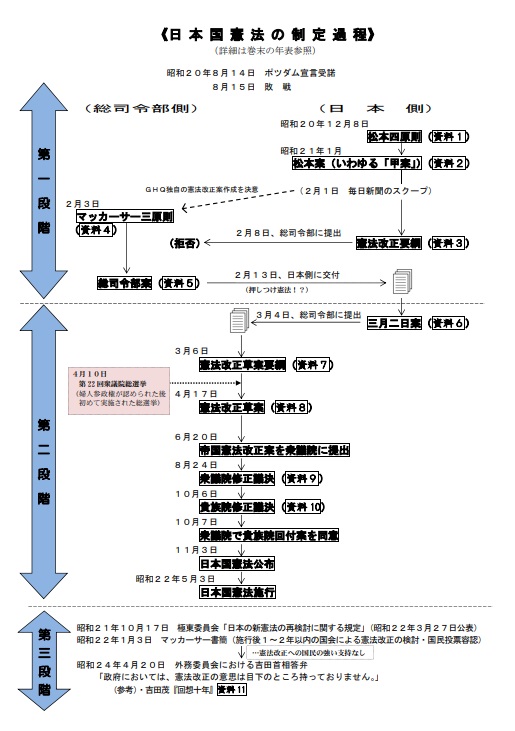
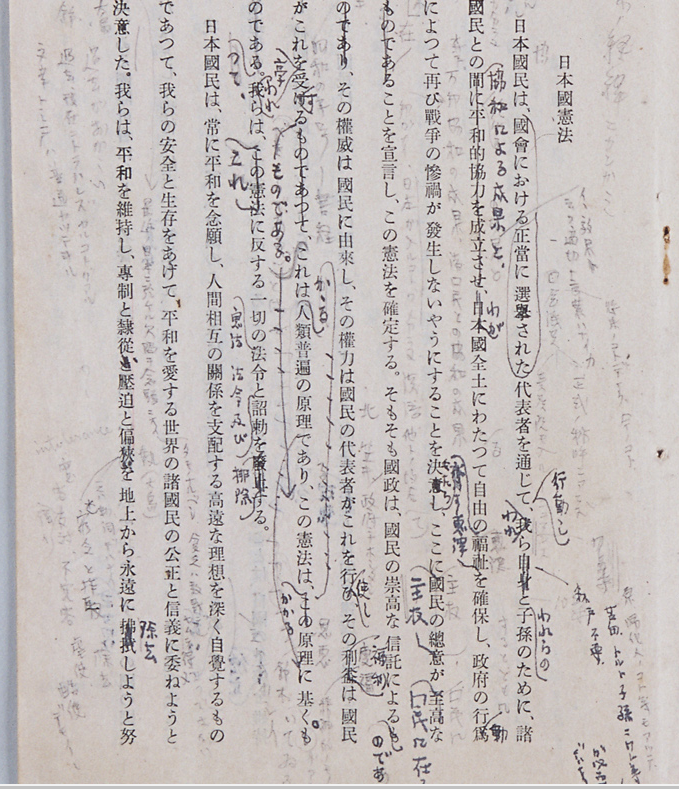

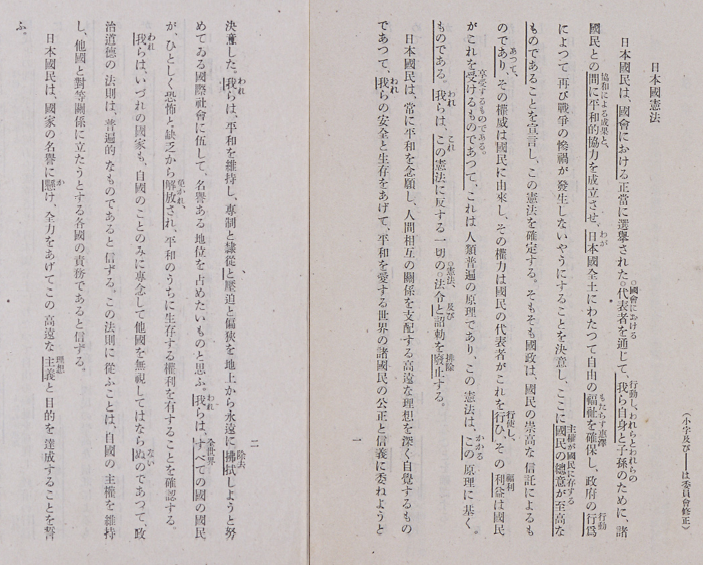


 一人は県内で勤めているし、末の女の子は埼玉の大学に行っている」と全面的に否定した。これは、新垣哲司氏(自民)の質問に答えたものだが、こうしたスキャンダルも官邸が内調にやらせていると考えられる。ネットや週刊誌などにデマを流し、これを議会で
一人は県内で勤めているし、末の女の子は埼玉の大学に行っている」と全面的に否定した。これは、新垣哲司氏(自民)の質問に答えたものだが、こうしたスキャンダルも官邸が内調にやらせていると考えられる。ネットや週刊誌などにデマを流し、これを議会で
