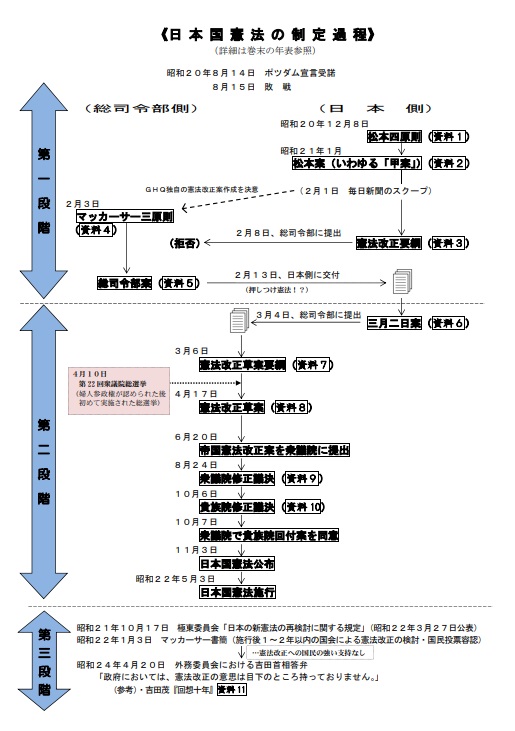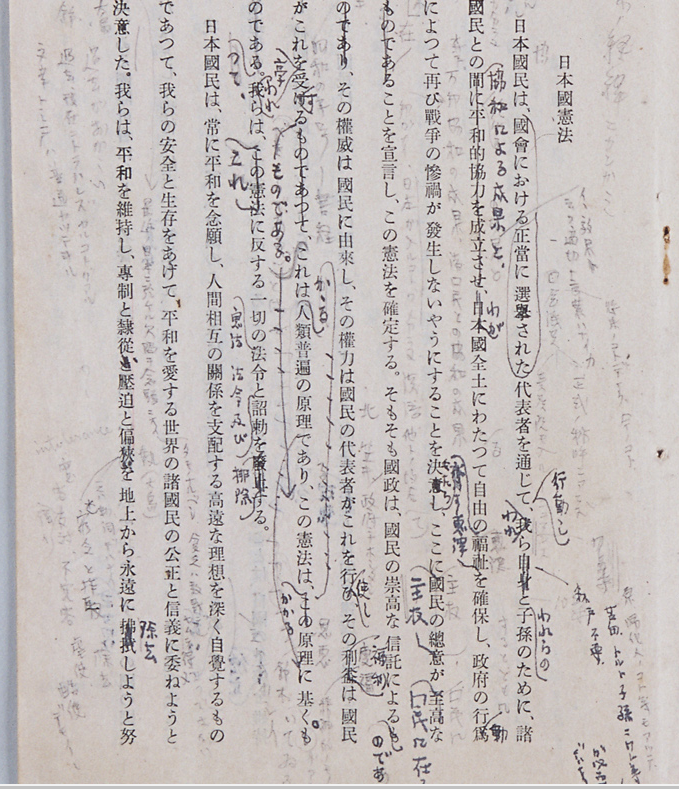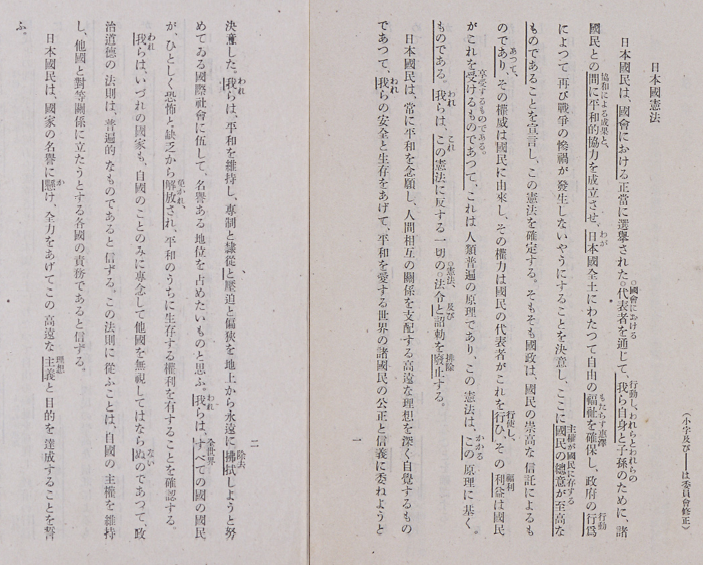内閣官房ー内調による行政介入を許すな!
菅首相が日本学術会議の推薦名簿のうち、6名の会員の任命を拒否したことで、「210人の会員で組織する」(日本学術会議法第七条)という規定に満たない違法状態が続いている。菅首相はこの6名の任命を何故拒否するのかという正当な理由すら説明出来ていない。
コロナ禍の「非常事態宣言」という情勢下にはあるものの、そのどさくさに紛れてこの問題をうやむやにすることは許されない。
ところで、この6名の任命拒否リストを作成した陰の人物が内閣官房副長官・杉田和博であると言われている。

杉田は1966年に警察庁に入庁したキャリアであり、1993年神奈川県警本部長を経て94年警察庁警備局長、97年から内閣情報調査室長。2001年1月の中央省庁組織改革により内閣情報調査室長が内閣情報官に格上げされたのを機に初代情報官。同年4月から内閣危機管理監に着任、2004年に退官し、JR東海顧問となり、同時に財団法人世界政経調査会会長に就任。
2012年に官僚に復帰し内閣官房副長官となり事務方のトップとなる。2017年からは内閣人事局長を兼務。
内閣官房副長官は日本のインテリジェンス機構を横断的に統括するポストであり、実体的な権力機構の要である。しかも、その同じ人物が霞が関の官僚の人事権を一手に握っているのである。
このような内閣官房への権力の集中は、戦前の内務省と同じような構造を示していないだろうか。
一)戦後、内務省の解体と内務官僚の残滓
内務省についてWikipediaには次のように記述されている。
日本の敗戦後、内務省は陸海軍の解体・廃止に伴う治安情勢の悪化に対応するために、警察力の増強と、特高警察の拡充を行うつもりでいた。1945年(昭和20年)8月24日、政府は「警察力整備拡充要綱」を閣議決定し、帝国陸軍・海軍と憲兵の解体によって、治安維持の全責任を内務省・警察が担うことを決めた。
1. 警察官数を現在の定員(9万2713人)の2倍にする。
2. 騒擾事件・集団的暴動・天災などに対処するため、集団的機動力をもつ「警備隊」
(2万人を常設し、必要あるときは4万人を一般警察官によって編成する)を設置す
る。陸海軍と憲兵なき現在の警察の装備では鎮圧が困難なので、軽機関銃・自動短
銃・小銃・自動貨車(トラック)・無線機などの武器や器材を整備して、「武装警察
隊」を設置する。
3.海軍なき後の領海内警備のために、水上警察を強化(1万人)する。
以上3つがその計画であり、警察を軍隊の代わりにすることを意図していた。1945年9月7日内務省は陸軍省・海軍省と協議し、復員軍人を警察官に吸収する計画を立てた。警備隊・武装察隊・水上警察の上級幹部として、陸軍大学校・海軍大学校出身者と優秀な憲兵将校を2,000人採用し警部補には陸軍士官学校・海軍兵学校出身者を充てることがその内容であった。
特高警察は大幅な拡充を計画し、「昭和21年度警察予算概算要求書」には、特高警察の拡充・強化のために1900 万円が要求されていた。内容は、①視察内偵の強化(共産主義運動、右翼その他の尖鋭分子、連合国進駐地域における不穏策動の防止)、②労働争議、小作争議の防止・取締り、③朝鮮人関係、④情報機能の整備、⑤港湾警備、⑥列車移動警察、⑦教養訓練(特高講習、特高資料の作成)の計7点である。
政府・内務省は、警察力の武装化と特高警察の拡充・強化によって、敗戦による未曽有の社会的悪条件の下にある民心の動揺を未然に防止し、不穏な策動を徹底的に防止することを企図していた。
1945年10月5日、日本政府はこれらの計画に対するGHQの許可を求めたが、GHQによって拒否された。それに先んじてその前日、GHQは特別高等警察や政府による検閲、更に国家神道の廃止を指示、さらに内務省のもとでの中央集権的な警察機構の解体・細分化を求めた。また、警保局や地方局を中心に公職追放の対象を提示した。
このGHQの方針を受けて中堅・若手の内務官僚は省最後の式典に集まり「必ず将来、内務省を復活させます」と、内務省の先輩に誓って解散したという秘話が伝えられている。また、内務省廃止の日に開かれた別れの酒宴で、居残り組(総理庁官房自治課)の中心である鈴木俊一は、内務省の先輩達に対して「私があとに残って、必ず内務省を元通り復活させてみせます」と誓ったとされている。
内務官僚の中堅幹部は一旦は公職追放された者も、52年頃には解除となり公職に復帰した者も多い。
一般に、帝国憲法下の内務省と言えば「特高警察」で悪名高いが、それが全てではない。地方行財政に対する強大な監督権(特に地方財政監督権)を持ち、警察、土木、衛生は勿論のこと、文部・農林・商工・交通、そして国家神道にいたる行政関係のすべてに対し非常に強い権限を行使していた。国家総動員体制が容易に進められたのも、このような中央集権的行政機関による統制力の強さがあったと言っていいだろう。
それ故、GHQは当初こうした中央集権的行政機構を解体しようとしたが、戦争で疲弊した地方を立て直し、早急に民生の安定を図るためには、その道に通じた内務官僚の力を借りざるを得なかった。加えて、戦後革命情勢と朝鮮戦争の勃発によって治安の安定化が求められ、親米反共の日本社会を形成するために内務省・警備警察(特高警察)の力を利用する必要に迫られたという事情もある。
こうして旧内務官僚たちは内務省復活の思いを秘めながら、後継組織となった現在の総務省、警察庁、国交省、厚労省などに分散し、またある者は地方行政官として、またある者は政府系機関や財界のシンクタンクとして、戦後社会の中に親米反共の保守的価値観を定着させるという戦略的役割を果たしてきたのである。
一方、「国家行政組織法」と同法に基づく各省庁「設置法」は内閣府以外の各省庁の任務・所管業務を細かく定めている。1948年、憲法と並行して作られたこの法律は、必ずしもGHQの主導で作られたという訳ではないが、戦前の中央集権化された内務省型の行政機構を解体し、国家による統制を分散させる結果をもたらした。
近年、自民党政権は「縦割り行政」の弊害や省益重視の官僚機構をことさらに批判し「行政改革」と称して省庁横断型の行政を進めようとしている。
しかし、それは必然的に内務省型の中央集権的な国家統制を志向するものとならざるを得ないということを忘れてはならない。
そうした中で、内閣総理大臣官房調査室として作られた諜報機関は最も旧内務省の性格を強く残した組織だと言えよう。そして省庁の所管業務や利害を超えて政府中枢の政策を左右する諮問機関としてまた権力の実体として影響力を強めることになる。
二)内閣情報調査室の歴史
① GHQの占領と朝鮮戦争の勃発

内閣情報調査室の歴史は、1950年の朝鮮戦争勃発から1952年のサンフランシスコ平和条約の発効という情勢を背景に、GHQが日本を反共防波堤として再軍備させようとしたことと吉田茂の日本版CIA構想に遡る。
・1950年 朝鮮戦争勃発。GHQが日本の再軍 備計画⇒警察
予備隊
・1952年 GHQ参謀2部(G2)部長のチャールズ・ウィロ
ビーのもとに軍事情報部歴史課の特務機関として「河辺機
関」が作られる。この「河辺機関」にはG2が認めた旧日
本軍の佐官級幹部が集められ、その多くを保安隊(警察予備隊が改変され、保安庁のもとに作られた自衛隊の前身組織)に入隊させた。
・この時、吉田内閣の軍事顧問であり、且つCIAの協力者(POLESTAR-5)でもあった辰巳栄
一は、吉田をGHQウィロビーと引き合わせ、警察予 備隊の隊
備隊の隊
員召集にも尽力した。
・また、辰巳は「河辺機関」ともかかわり、その後「河辺機
関」が「睦隣会」に名称を変え「官房調査室・別班」として
活動を開始するまでその中心的役割を担った。これが現在の「世界政経調査会」である。

②吉田茂の日本版CIA構想
・サンフランシスコ講和条約の発効を目前にし、対共産圏を睨んだ総理府の情報機関設立が計
画された。それはソ連や中国など「共産圏」の動向はもとより、軍事力を奪われた日本が情
報を武器として外交交渉を有利に進めるために、世界の情報を収集することが重要であると
いう考えによるものであった。
他方、GHQは占領期間中、参謀第2部(G2)のウィロビー部長が中心になって諜報活動を行
い キャノン機関など工作機関ももっていた。しかし、これらの活動も占領終了とともに形
式上は終了する。そこで、その代替として、アメリカが大戦中の諜報機関を改編して作った
中央情報局(CIA)を参考に、日本版CIAを作るという構想が持ち上がった。
・この構想は、吉田にとってはGHQが撤退した後の国内の共産党をはじめとした左翼勢力の情
報を収集・監視する総合情報収集機関を設置したいという考えとも合致していた。
・また、当時官房長官だった緒方竹虎(朝日新聞副社長)は日本版CIAとして世界水準の情
報機関へと拡大する構想を描いていた。彼自身もCIAと緊密な関係を持っており、CIAもこ
の構想のための財政支援もしていた。
・吉田は、この構想を緒方竹虎内閣官房長官に委ね、この調査機関を土台として、組織の拡張
または別組織の立ち上げを行うことで日本のインテリジェンス機能を強化しようと考えた。
当時は、戦前に大陸にばらまいてあった諜報網がまだ生き残っていた。いうまでもなく、ア
メリカが一番知りたいのはソ連や中国共産党の情報だった。占領期間中は辰巳を始め旧軍関
係者がウィロビーたちに協力し、情報を供与していた。この中国情報と交換でアメリカCIA
から情報提供を受けるというところまで話は進んでいた。
ところが、敗戦前からの遺産は、時間とともに色あせ、戦後のアメリカが必要としている情
報としては新鮮味のないものとなっていた。もう一つ決定的なことに、CIA は秘密保護法を
もたない日本は、情報漏洩の危険性が高く情報をバーターできないと考えていた。他方、外
務省は内調が対外情報の分野に入り込んでくることに強い警戒感を持っていた。
・緒方は内調を「世界中の情報を全てキャッチできるセンターにする」という構想を持って
いたがこれに対して読売新聞をはじめとする全国紙が「内調の新設は戦前(世論形成のプロ
パガンダと思想取り締まりを行い)マスコミを統制した情報局の復活だ」として反対運動を
展開した。これにより一気に世論の批判が噴出する。そしてこの構想は国会で潰される事に
なる。
③内閣情報室の設置
・結局、「弱いウサギは、長くて大きな耳を持つ」という日本版CIA構想は頓挫する。吉田は
国家地方警察本部、外務省、法務府特別審査局にそれぞれ情報機関設置のための案を作らせ
国警の村井順が「内閣情報室設置運用要綱」を、外務省が「内閣情報局設置計画書」を、法
務府特別審査局が「破壊活動の実態を国民に周知させる方法等について」をそれぞれ提出し
た。こうして採用された村井案に基づいて内閣総理大臣官房調査室(のちの内閣調査室)が
政令によって作られ、キャノン機関の推薦もあって、初代室長には警察官僚の村井順が就任
した。
※ キャノン機関はG 2直属の情報機関であり、多数の日本人工作員を組織し、河辺機関の他にも柿の木坂機関、矢板機関、日高機関、伊藤機関等の工作員組織を傘下においていた。当時すでにアメリカとソ連との対立が顕在化し、また朝鮮半島での緊張も高まるなかで、主に朝鮮半島情報の収集やソ連スパイの摘発とともに、日本国内の共産主義勢力を弱体化させることを任務としていた。
当時、レッドパージ・公職追放が進められる中で、共産党員やその同調勢力に対する弾圧の実践部隊
・国家警察本部の警備課長であった村井は、G2(参謀第二部、検閲や諜報)、CIC(対敵諜
報部隊)CID(犯罪捜査局)への報告や連絡を忠実に実行したことがキャノンに評価された
のだろう。
しかし、初代室長となった村井順は、海外出張時に外務省が仕組んだとみられるトラブルに巻き込まれ失脚する。この後、調査室が大規模な「中央情報機関」となる事はなかった。当時の世論がそれを許さなかったからである。
マスコミや世論の大きな批判と警戒の中で発足した内調は、幾度かの改変を経ながら今日に引き継がれてきた。そして現在においては、外事・公安警察、公安調査庁、防衛省情報本部等のインテリジェンス機構との連携を深めつつ、国家の意思決定において極めて大きな影響力を持つに至っている。
その一方で、独自の対外的情報網という点では他の先進諸国に比べて充実しているとは言えない。日本が独自の軍事戦略を持てないのはそれも大きく作用しているとは言えないだろうか。
④親米反共の国内体制―治安政策のための諜報組織
設立当初は、村井以下わずか4人(村井順、三枝三郎、岡正義、志垣民郎)ではじまった官房調査室 〔『内閣調査室秘録』〕の活動は、初めから国内治安を意識した反共工作、左翼的政党や戦後民主主義の推進者に転じた知識人・言論人を籠絡し、牙を抜き去ることだった。その背景には左の表に列挙したような「平和と民主主義」を求める民衆の闘いがあり、日米支配層はこれが共産主義思想と結びついて戦後革命に発展することを何よりも恐れていたのである。そして、今日に至っても内調の役割が思想統制と人民の監視にあることは全く変わっていない。むしろ、ますます旧内務省時代の特高的な動きを加速させていると見ていいだろう。
〔『内閣調査室秘録』〕の活動は、初めから国内治安を意識した反共工作、左翼的政党や戦後民主主義の推進者に転じた知識人・言論人を籠絡し、牙を抜き去ることだった。その背景には左の表に列挙したような「平和と民主主義」を求める民衆の闘いがあり、日米支配層はこれが共産主義思想と結びついて戦後革命に発展することを何よりも恐れていたのである。そして、今日に至っても内調の役割が思想統制と人民の監視にあることは全く変わっていない。むしろ、ますます旧内務省時代の特高的な動きを加速させていると見ていいだろう。
三)内閣情報調査室の変遷
このように、対外的な諜報機関としては制約された、しかし国内的には徹底した治安の観点からのインテリジェンス機構として出発したのが内閣官房調査室である。そして、これは何度かの組織改編を経て今日に至っているが、その基礎を作っているのは旧内務省の特別高等警察=特高であり、旧日本軍の諜報部隊出身者である。さらに、その形成過程が①に見たように、中国革命―朝鮮戦争に続く戦後革命への人民の闘いのうねり、とりわけ国労や教育労働者の闘いを軸とした労働運動の高揚に対する予防反革命としての役割を担っていた。同時に反共防波堤としての日本帝国主義がその城内平和を維持するための思想監視とプロパガンダのための組織として成長してきたのである。
そして、内閣情報調査室は今日、各省庁の情報機関、警察、公安調査庁、自衛隊、さらに民間の情報組織、報道機関等、あらゆる組織の中に根を張り、それは戦前の情報局を凌ぐ組織となっていることを見逃すわけにはいかない。この組織は「平和」な時にはもっぱら世論を誘導し保守的価値観を拡散するプロパガンダを、階級対立が深まり政権が危機に陥ったときは、政権に批判的な(あるいは反米的な!)市民、及び行政職員・官僚たちの動向を監視し、これを籠絡し、潰しにかかる「特高警察」の顔として立ち現われるのである。
また、これは自民党政権下は言うに及ばず、政権の交代が行われようと変わることなく一貫して継承されてきたのである。
<冷戦時代の内調>
1952年4月 内閣総理大臣官房調査室(第三次吉田内閣)
初代室長 村井 順(吉田総理秘書官、国家地方警察本部警備第一課長)⇒ 1953 年12
月に更迭
1955年 国際部に「軍事班」が設けられ、元海軍中佐の久住忠男らを中心としてベトナム戦争の推移や沖縄に駐留するアメリカ軍の動向などを観察。
1957年8月1日 内閣法(法律)の一部改正、内閣総理大臣官房調査室が廃止され、内閣官房の組織として内閣調査室を設置。

60年安保をきっかけに内調は論壇の流れをフォローするようになり、安全保障論の育成のために中村菊男、高坂正堯、若泉敬、小谷秀二郎ら現実主義的な論客の結集を助け、論議を普及するなどした。現在でも内調は勉強会を数多く行っており、学識経験者や企業を招いて情勢分析を聞くなどしている。
1977年(昭和52年)1月1日には内閣調査室組織規則の施行により、内部体制が総務部門、国内部門、国際部門、経済部門、資料部門の5部門となる。
1986年7月1日に内閣官房組織令の一部改正により、「内閣調査室」から現在の「内閣情報調査室」となる(5部門体制は継承)
<冷戦後の内調>
1995年 阪神・淡路大震災が発生。この際、政府の立ち上がりが遅れた教訓から1996年5月11日に内閣情報調査室組織規則の一部改正し、内閣情報集約センターを新設。大災害の際には官邸が自衛隊機を飛ばすなど、積極的な情報収集を行い、また民間との協力体制の確立、マスコミへの情報発信等の情報収集・危機管理体制の改革が行われた。
1998年10月 情報関係機関の連絡調整を図り、国内外の重要政策に関する情報の総合的把握を目的として「内閣情報会議」が閣内に設けられた。これは、内閣官房長官が主宰する次官級の会議で年2回ほど開催される。そして、その下に設置されたのが「合同情報会議」である。内閣官房副長官が主宰する隔週の会議。省庁横断的な情報関係機関の実務者による会議である。事実上、戦前のような「情報局」が法的根拠を持たないまま作られているということである。
そして、この庶務を行なっているのが内閣情報調査室である。
【資料】
■ 内閣情報調査室
内閣官房組織令第4条によって設置された内閣官房に属する組織。内閣情報調査室194名と内閣衛星情報センター221名からなり、総勢415名である。

内調の下部組織の内閣衛星情報センターは、情報収集衛星や外国の商用衛星の画像を用いてイミント(画像諜報)を行っている。また、アメリカ合衆国中央情報局(CIA)・イギリス秘密情報部(SIS)などの外国政府情報機関との間では対等な関係を築いている。
さらに内閣情報調査室は内閣官房副長官が主宰する合同情報会議(隔週)、内閣官房長官が主宰する内閣情報会議(年2回)の庶務を担っている。
■民間情報組織
内閣官房予算から情報委託費が支出されている民間の情報調査、プロパガンダを担っている組織は非常に多い。その中でも主要な組織としては以下の団体がある。
【財団法人 世界政経調査会】
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)参謀第2部(G2)所属の対敵諜報部隊(CIC)の下請け機関として設立された、旧軍人による情報収集グループである特務機関「河辺機関」がその後、「睦隣会」に名称変更され、それを母体として、内閣調査室のシンクタンクとして設立された。
所在地:東京都港区赤坂2-10-8
会長 2005年7月~ 杉田和博 (現内閣官房副長官)
2013年2月~現在 植松信一(三井住友銀行顧問)
<設立時の主要メンバー>
●河辺虎四郎(陸軍中将、陸士24期、参謀次長)
●下村 定(陸軍大将、陸士20期、陸軍大臣)
●有末 精三(陸軍中将、陸士29期、参謀本部第2部長、対連合軍陸軍連絡委員長)
●辰巳 栄一(陸軍中将、陸士27期、第12方面軍参謀長、第3師団長)
●芳仲和太郎(陸軍中将、陸士27期、フランス大使館駐在員、トルコ大使館付武官、ハンガ
リー大使館付武官、西部軍管区参謀長兼第第16方面軍参謀長、第86師団長)
●山本茂一郎(陸軍少将、陸士31期、第16軍参謀長兼ジャワ軍政監)
●西郷 従吾(陸軍大佐、陸士36期、オーストリア大使館付武官、大本営ドイツ班参謀、
南方軍参謀緬甸方面軍参謀、第23軍参謀、第20軍高級参謀)
●萩 三郎(陸軍中将、陸士29期、北部軍管区参謀長兼第5方面軍参謀長、札幌復員局長)
●真田穣一郎(陸軍少将、陸士31期、大本営作戦部長、陸軍省軍務局長)
●佐々木勘之丞(陸軍少将、陸士28期、陸軍中野学校学生隊長)
●石戸 勇一(陸軍大佐、陸士30期、太原特務機関長)
●甲谷 悦雄(陸軍大佐、陸士35期、参謀本部ソ連課参謀、ソ連大使館付武官輔、大本営戦争
指導課長、ドイツ大使館付武官輔佐官、公安調査庁参事官、KDK研究所長)
【国際情勢研究所】
一般財団法人世界政経調査会の研究部門。内外情勢の分析、判断やそのための調査・研究。研究会等を開催。2億円程度の収入の90%以上が内閣官房から情報調査委託費。
役員には元警察官僚が名を連ねている
所在地 東京都港区西新橋3-24-9 飯田ビル7階
会長 折田 正樹(東大政治学科 外務省入省 宇野、海部内閣の大臣秘書官を経て外交官)
【一般社団法人 内外情勢調査会】
国内外の情報の収集・調査・分析を行い、それに基づいた啓蒙をするのが主要な目的である。世論形成のプロパガンダ機関。
政財界・官庁などの首脳、自治体首長、海外の駐日大使等の著名な専門家による講演会を開催し「国民の知識向上と理解増進」を諮るということになっている。
理事には、内閣情報調査室への出向経験がある元警察官僚、元外務官僚、元大蔵官僚が名を連ねている。
付録)
「戦後日本の国家保守主義――内務・自治官僚の軌跡」(中野晃一)
この本へのレビュアーを一部転載する。
中曽根康弘や正力松太郎/小林與三次(よそじ)等、特高/内務省関係者が戦後どこに異動したかを淡々と追うことで、前近代的な日本の超国家主義がどう現代に繋がっているか、そして中曽根康弘からの新自由主義がどう超国家主義を自壊させ、形骸だけの道徳/暴力国家が誕生したのか、を浮かび上がらせようという意欲作。
・小林與三次は、メディアの官報化を目指す「日本広報協
会」会長や読売新聞/日本TV社長へ
・鈴木俊一は、考えない社会を目指す「日本善行会」会長
へ
・林 忠雄は、国畜化を推進する「地方自治情報センター」
理事長へ
・石原信雄は、ブラック労働を推進する「パソナ」アドバイザリー・ボード代表へ
・柴田 護/花岡 圭三/小林 実は、自治の名の元に不透明な機関を支援する「日本宝くじ協会」理事長へ
・警視庁警備局長/内閣情報調査室長/内閣情報官/内閣危機管理監を歴任した公安畑出身の杉田和博は、1994年に東電
顧問に天下りした後、2012年末第二次安倍内閣の官房副長官に
・中曽根康弘以降の新自由主義推進は「国家に過度な負担をかけることなく前近代的な規範の下に国民を統合する」
国家保守主義と親和性があったが、官僚が国家の権威を傘に着て自らの権益を確保することで国家保守主義の空洞
化を招き、第二次安倍内閣の「心のノート」等の洗脳教育である「道徳」や、杉田和博のような公安官僚登用や軍
事費増額、そして近代憲法の廃止のような暴力による保守的国民統合が図られるようになった。
中曽根臨調や小泉靖国参拝など、国家保守主義が自滅して暴走してきた様子を、多くの人が知ることは大事なことかと思います。地味な本ですが、大事な視点でした。(Utah)
戦前の日本では、内務省は内政・民政の中心となる行政機関であり、「国家の中の国家」と呼ばれるほど権勢を振るった。
戦後、1947年に内務省は廃止されたが、自治庁(現在の総務省)、警察庁、国土交通省、および厚生労働省へと人脈は引き継がれていく。本書は、旧内務省・自治省等の幹部クラスの人事(本省から天下り先まで)を丹念にデータベース化し、それを分析したものである。この分析により、戦前も戦後も変わらない「官僚主権国家」の骨格を、レントゲン写真のように見事にあぶりだした労作である。
本書は、「国家の権威のもとに保守的な価値秩序へと国民の統合を図る政治思想とその制度的な基盤」を「国家保守主義」と名付けている(「おわりに」より)。この保守思想は、1970年代末から時代の変化に合わせて、新自由主義的転換(つまり弱肉強食の推奨)を図り、現在に至っている。かつての保守主義は、「国民統合」の欺瞞を続けるために、復古的歴史認識、復古的道徳教育、軍国主義など、空疎極まりない、理念なき「保守主義」と化した。この事実は、近隣諸国ばかりか、欧米諸国からも見透かされていることは、最近の報道から明らかであろう。
税金による雇われ人に過ぎない官僚が権力を振るうには、「虎の威」を借りることが不可欠である。官僚にとっての「虎の威」は、戦前は天皇であり、戦後は対米従属である。官僚から見れば、国民は「愚民」であり、政治家などは、「官僚の掌で踊るしかない無知な木偶の坊」でしかない。本書で分析されたように、旧内務省人脈だけに限っても、得体のしれない多数の天下り団体を設立し、その幹部に天下るのが、常態化されている。「官僚主権国家」は、官僚が国民にたかり続ける「シロアリ国家」そのものである。
本書の分析を参考にすれば、日頃は無知な政治家の陰に隠れている「官僚主権国家」が、その本性を剥き出しにするのは、その利権が脅かされた時であることが分かる。特別会計の闇を暴いたことが無関係とは考えられない、石井紘基議員の刺殺事件(2002年)、西松建設の違法献金事件で「自民党に捜査が及ばない」と発言した漆間巌内閣官房副長官(警察庁出身)(2009年)などはその片鱗である。最近では、警察庁出身の内閣官房副長官が中心となってまとめた秘密保護法がある。この法律こそ、「官僚主権国家」が、官僚の掌で踊る政治家達を抱き込んで成立させた稀代の悪法である。本書は、「国家保守主義」がなりふり構わず秘密保護法に突き進んでいった背景を深く理解させてくれる。(つくしん坊)


 つまり、予算そのものは非常に硬直化していて自由度がない。
つまり、予算そのものは非常に硬直化していて自由度がない。